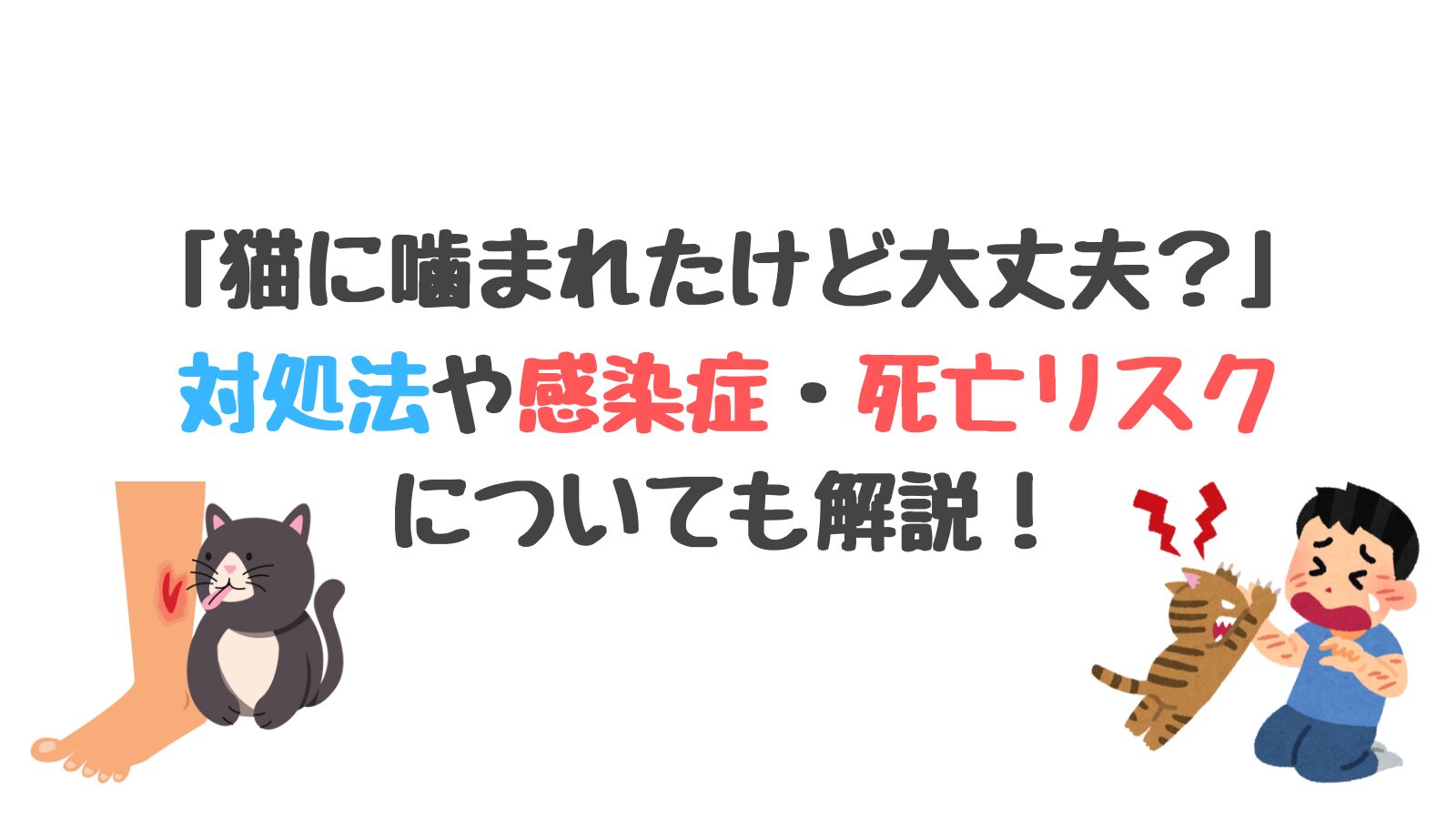【目の病気】猫の眼瞼内反症ってどんな病気?症状、原因、治療法はあるの?

この記事は、このような方へ向けて書いています↓
「最近、○○だな〜」
「飼い猫が眼瞼内反症と診断された」
「眼瞼内反症の症状、原因、治療法について詳しく知りたい!」
初めての方でもわかりやすいように説明するので、安心してくださいね
それでは、いきましょう!
「眼瞼内反症」ってどんな病気?

猫の眼瞼内反症(がんけんないはんしょう)は、眼の問題の一つで、通常は眼瞼(まぶた)の一部が内側に巻き込まれている状態のことをいいます。これにより、まぶたの毛や皮膚が眼球にこすれたり、刺激されたりして、猫の目に不快感や痛みを引き起こす病気です
「眼瞼内反症」の症状は?

目の充血
猫の目が充血することにより赤くなることがあります。また、まぶたの刺激により目の血管が膨張し赤くなることもあります
目やに
猫の目から多量の目やに(目の分泌物)が出ることがあります。まぶたが内側に巻き込まれているため涙液が正常に排出されず、目やにが溜まりやすくなることが原因です
まぶたの炎症
炎症が生じまぶたが赤く腫れることがあります。まぶたが内側に押し付けられることにより、炎症が引き起こされます
目をこすり続ける行動
痛みや不快感を和らげるために、猫が目をこすったり、顔をこすったりすることがあります。このような行動をとる場合は痛みを感じている可能性が高いです
眼球の傷害
長期間のあいだ放置すると、眼瞼内反症により眼球そのものが損傷してしまう可能性があります。また、まぶたの毛や皮膚が眼球にこすれることで角膜や結膜が損傷することもあります
「眼瞼内反症」に痛みはあるの?

猫によって異なりますが、眼瞼内反症は一般的に痛みや不快感を感じやすい病気になります。目をこすったり、不快そうな行動を見せたりする場合、眼瞼内反症の可能性が高いです。飼い猫にこれらの症状が現れた場合は、速やかにかかりつけの獣医師に相談し、適切な治療を受けることが大切です。眼瞼内反症がどれだけ進行しているかにもよりますが、治療には手術が必要な場合もあります。
「眼瞼内反症」の原因

先天性
先天性とは生まれつき持っている状態のことをいい、まぶたの形状が正常でないことにより眼瞼内反症が発生します。この場合、遺伝的な要因や品種に関する問題があるとされていて、特定の猫種には眼瞼内反症がでやすい傾向にあります
加齢
猫は年をとると、まぶたの組織が弛み(たるみ)やすくなり、眼瞼内反症にかかるリスクが増加します。老齢による眼瞼内反症は後天性のものとされています
外傷
まぶたに外傷が加わると、まぶたの形状が変化し眼瞼内反症を発症する可能性があります。傷害やケガが原因でまぶたが引っ張られたり、内側に引き込まれたりすることにより発症することもあります
炎症
目のまわりの炎症や皮膚の状態が悪化すると、まぶたの形状が変化し、眼瞼内反症を発症することがあります
「眼瞼内反症」の治療法、治療費は?

1 眼薬または抗生物質の処方
軽度の眼瞼内反症の場合、眼薬や抗生物質の処方による治療を行います。目薬の場合、抗炎症剤や角膜の保護を目的として使用し、眼球や眼の周辺組織に感染が存在する場合は抗生物質の目薬を併用することもあります
治療費
月に5,000円前後になります。一般的には低価格ですが、ほかの病気が原因で症状が出ている場合、獣医師によって価格の変化があります
2 手術
重度の眼瞼内反症の場合、外科手術による治療を行います。治療法は、皮膚の内反した部分を切除して矯正する方法です
治療費
10万〜20万円前後になります。外科手術は軽度の眼瞼内反症と違い、とても高額な治療法となっています。もちろん、獣医師によって価格の前後はありますが、一般的にはこれくらいかかると考えておきましょう。重度の眼瞼内反症は飼い猫だけでなく、飼い主さんにも大きな負担がかかります。軽度の症状に見えても早めの受診をし、早期発見するよう心がけることが大切です
「眼瞼内反症」は治るの?

結論、治ります。前述した治療法や治療費はかかりますが、完治することが可能な病気です。もちろん手術なので必ず成功するとは言えませんが、成功するかしないかは症状の状態によって変わってくるので、早期に適切な治療を受けることが大切です
「眼瞼内反症」の予防法について

猫の眼瞼内反症は遺伝に関連していることがあるため、完全に予防することは難しい病気です。ただし、いくつかの注意事項やケアの方法によって猫の目の健康をサポートすることで、発症リスクを低減することができます
1 日頃から目に異常がないか確認する
猫の目の異常を早期に発見するために、定期的な目のチェックをしましょう。目の充血や普段と違う分泌物などの症状が見られたら獣医師に相談するようにしましょう
2 環境を整える
猫が過ごす生活環境はできるだけ清潔に保つようにしましょう。そうすることで猫が外傷を負うリスクを軽減することができます。尖ったものや鋭利な障害物などがないか確認し、猫の生活環境からは遠ざけるようにしましょう
3 定期的な健康診断
少なくとも年1回の健康診断を受けるようにしましょう。お勧めは半年に1回です。定期的な健康診断を行うことで病気の早期発見だけでなく、遺伝的要因の健康問題も見つけることができます
ペット保険に入ろう

飼い猫の急病やケガで治療費や入院費がかかる場合、高額な値段になるケースがほとんどですが、ペット保険に入ることでそのような問題がカバーされ、飼い主さんの精神的にも安心します。また近年のペット保険は一律の値段ではなく、予算や飼い猫の健康状態に合ったプランを選択することができます